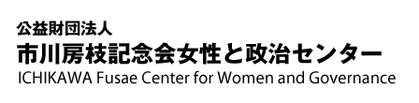講師の保阪正康さんはノンフィクション作家で日本文藝家協会・日本ペンクラブ会員。「昭和史を語り継ぐ会」を主宰している。
女性史の権利獲得運動の専門家ではないが、近現代史を検証していくと、当然ながらそういうテーマに出会う。その中で何がわかり何が重要なのか。市川房枝という1人の女性が、近現代史の中ではどういう位置づけになるかを考えるために、はじめに近現代史の大まかな枠組みを話したい。
日本の国際社会へのスタートは1858(安政5)年の開国に始まり、67(慶応3)年大政奉還を経て69(明治2)年明治新政府が誕生する。89(明治22)年大日本帝国憲法ができるまでの20年間はどんな国を作るかという日本の闘いで、4つの国家像があった。①帝国主義国家 ②帝国主義的道徳国家 ③自由民権国家 ④連邦制国家である。結局政府は帝国主義国家を選び西欧の真似をするが、②③④は死んだわけではなく、それぞれの思想は歴史の中の地下水脈的にずっと社会に流れて行き、近代日本の中に時々噴出してくる。明治の終りあるいは大正時代に、社会の矛盾に気づいた人たちが何かの意思を表していく時に浮上し、その時の運動を検証すると、どの流れを汲んでいるかわかる。例えば 1918(大正7)年の富山の米よこせ運動のエネルギーは、自由民権運動などの流れをくんでいると言える。
1911(明治44)年は明治政府があらゆるものを立法化し、大逆事件も起こった年だ。そういう背景の中で平塚らいてうが『青鞜』を発行し、「原始女性は太陽であった」という名文を書いた。4つの国家像のどれが、らいてうらの後押しをしたのか。
歴史の流れや動きの中に内在しているものは、その時に消えても歴史の中で底流として地下水脈で流れて行く。誰かが新たに行動を起こした時に、必ず結びつく。市川房枝は何と触れ合ったのだろうか。どういう形で自分たちの主張に組み込んでいったのだろうか。
市川の講演は聞いたことがあるが2人で会ったことはない。国会議員のタイプには2つあり、強調的な論の中に自分を置き、常に論が先に来る人。もう1つは人が先に来て後ろに論がある人。市川は紛れもなく「私」がいて、後ろに「論」がある人。だからこそ人間的な魅力が出るのだと思う。
市川は教師を経て新聞記者になったが、戦前の女性運動の活動家たちを見ると、新聞記者になることは、女性が社会化していくときの通過儀礼のようなものだった。問題意識との出会いである。市川は歴史に使われた人だと解釈している。歴史に使われるとは、その人がいやだと言っても、お前にはこの役を与えたんだよと思われるような人。歴史そのものには意思があり、個人というものを超えた形で存在して行く。市川は1つのスローガンを婦人の権利獲得という茫洋としたものではなく、婦選獲得運動という具体的な形で問題提起した。それが歴史に使われるということだ。婦人参政権はいろんなものを混ぜあわせながら、運動そのものとして包含していくと同時に、市川の眼は個人の眼ではなくなってくる。ある意味では市川個人としては死ぬが、この混ぜ合わせになっていた眼は残り、その眼はいろんな人たちに降りてくる。
市川の生き方は婦選獲得運動の歴史になっていて、市川を書くことによって歴史に使われた市川の婦人参政権の歴史が整理される。その人が生きた姿の中に何かに使われた、その人自身が自分を捨てた、ということがある時に、その人の人生が固有名詞だけではない人生だったとわかる。市川房枝という個人は失ったけれど、彼女が持っていた歴史の中の様々な眼や、軌跡の中の天に使われた部分は残っている。4つの国家像の流れが歴史の地下水脈に眠っているように、市川さんも地下水脈の中に眠って行くのだろう。(や)