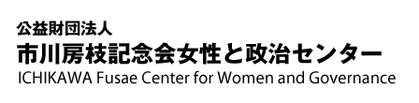「日本の原発政策はなぜ失敗するのか」金子勝さん(立教大学特任教授・慶応義塾大学名誉教授)/ドキュメンタリー映画「小さき声のカノン」/「被ばくを軽視してはいけない」鎌仲ひとみさん(映画監督)
午前中は経済学者、金子勝さんが講演。再生可能エネルギーが日本で「主力電源」になり得ない理由、日本の原発政策が失敗する理由を解説した。
再エネ普及に舵を切り、原発の依存度を低減するとしながら原発を「重要なベースロード電源」と位置づけ、再稼働を推進することとしたのは論理矛盾だ。なぜならば、「第5次エネルギー基本計画」が想定する2030年度原発比率を20〜22%とするには約30基の原発を稼働させる必要がある。しかし現在、新規制基準の下で再稼働したのは9基で、今後17基が続くとするが、現在の原発を40年で廃炉にする前提だと2030年に動かせるのは18基。その中には、東海地震の震源地に近い浜岡3号機や、中越沖地震で被災した柏崎刈羽4・6・7号機、東日本大震災で被災した女川原発2・3号機なども含まれている。となると、2030年に30基を動かすにはすべての原発を60年稼働することが前提となり、これでは福島第一原発事故の反省は全くない。
原発を多数動かす理由は、そうしないと1基当たりの発電コストが高くなり、原発が「安いエネルギー」ではないことが露呈してしまうからだ。他方、福島第1原発の事故処理費用が11兆円から約22兆円に倍増した。また基本計画は、原発を「運転コストが低廉で変動も少なく、運転時には温室効果ガスの排出も少ないことから~」として重要なベースロード電源だと述べているが、原発のコストを「運転コスト」に限定している点は要注意だ。
福島の事故後、原発を新設するコストは世界では少なくとも1基1兆円以上となったが、日本は4400億円としてきた。原発新設の話になると、原発の発電コストが他のエネルギーより高いことが表面化する。これは、経産省・資源エネルギー庁が進めてきた原発輸出がすべて失敗している事実について触れられないことと裏腹であり、世界で原発は過去のエネルギーになりつつある現実を認めたくないからだろう。
金子さんは、このように原発政策の矛盾や核燃料サイクル事業の欺瞞も突き、既得権益の塊である「原子力ムラ」を解体して電力の大改革を行わない限り、再生可能エネルギーの普及とエネルギー転換はできないと強調した。
午後は、福島第1原発事故後、子どもたちの健康を守るために奮闘する母親たちの姿を追ったドキュメンタリー映画「小さき声のカノン」上映後、同映画を制作した鎌仲ひとみ監督が「被ばくを軽視してはいけない 低線量かつ慢性被ばくがもたらすもの」をテーマに語った。
イラクでは湾岸戦争後、子どもたちにガンや白血病が多発したが、これは劣化ウラン弾による内部被ばくだった。原発の燃料を作る過程で出る廃棄物を軍事利用した劣化ウラン弾の放射線は、人体に影響はないと言われているが、そのメカニズムは外部被ばくと全く違い、「命の根っこがくじかれる=ありとあらゆる生命機序(しくみ)の危機」であると、被ばく医師・肥田舜太郎(2017年没)は内部被ばくの怖さを指摘した。
福島で起きている被ばくは従来の被ばく影響モデルでは説明できないのではないか。低線量の被ばくを長期間受け続けると内部被ばくが慢性化し、その被ばくから子どもたちを守るにはどうしたらよいのか。チェルノブイリ事故から32年経ったが、ベラルーシでは今も毎年甲状腺移動健診を続けており、小児甲状腺がんのピークが過ぎても全体の患者数は増えたままで、この傾向は100年続くと考えられている。またベラルーシでは、国内の14カ所以上ある国立の保養施設で毎年、3歳から18歳までの45,000人の子どもたちが最低21日以上の保養を国家予算で受けている。そこでは学びながら滞在し、専門家が常駐し、質の高い食事が提供される。保養により、内部被ばく量は激減する。
福島に子どもたちが住み続けるなら、1年に最低1回、21日間、1mSv/年以下の地域での保養を制度化すべきであり、原発事故子ども被災者支援法の実施が急務だ。
自身が浴びた取材中の被ばくリスクも語りながら、鎌仲監督は放射能汚染とどう向き合うか(=命をどう守るか)、放射線から住民を守るためには空間線量だけでなく、土壌汚染地図を作成し、情報公開することが大事だと訴えた。